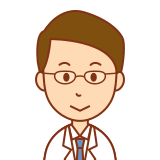
コロナの5類への移行後、様々な感染症が流行しており、最近はリンゴ病(伝染性紅斑)の患者数が非常に増加しています。
妊婦さんがかかるとおなかの赤ちゃんに悪影響が出る場合があるため、妊婦さんや妊活中の方は注意が必要です。
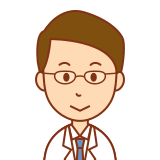
要点は以下になります。
①抗体を持っていない妊婦の場合、非流行期では1%、流行期では10%が妊娠中に初感染する。
②妊娠中の初感染では、約5%ではあるが、胎児貧血や胎児水腫を引き起こす。最重症例では胎児死亡も起こりうる。
③他者への感染力があるのは症状出現前5日間ほどであり、典型的な症状出現時(=診断がつく時期)には、既に他者への感染力は無い。そのため、家庭内、学校や保育園、職場等で感染が拡大しやすい。
④日本では約50%の妊婦は既に抗体を持っており、感染の心配が無い。そのため、感染流行期には、妊娠前や妊娠判明時に抗体(IgG)検査がbetter(IgG抗体陽性なら、基本感染の心配が無いため)。
⑤抗体検査をしていない人や抗体を持っていない人は、徹底した感染予防が重要。同居家族の感染予防も非常に重要。
1)リンゴ病(伝染性紅斑)とは
ヒトパルボウイルスB19というウイルスによって引き起こされる感染症です。
子供に多く見られる病気で、発疹が特徴的です。両頬に赤い斑点が現れ、りんごの様な頬に見えることから「リンゴ病」と呼ばれます。子供は、かかっても軽症ですむケースが大半です。
大人の場合は、感染しても約半数は無症状と言われています。
【主な症状】・両頬の赤い斑点 ・感冒様症状 ・関節痛
【感染経路】飛沫感染・接触感染。患者の唾液、痰、鼻水を介して感染する。
【感染後の経過】
1)5~10日の潜伏期間を経て、ウイルス血症となる。この期間は5日間ほど持続し、無症状か感冒様症状のみの場合が大半である。
2)ウイルス血症が改善したころ(=感染から2週間前後)に、典型的な症状(特徴的な皮疹、関節痛 等)が出現して、リンゴ病と診断可能になる。症状は1週間ほど持続する。
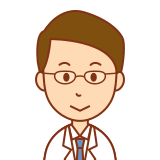
そして、非常に重要なので繰り返しますが。
感染力があるのはウイルス血症の時期=典型的な症状出現前5日間ほどであり、症状出現時(=診断がつく時期)には、既に他者への感染力はありません。
2)妊婦とリンゴ病 ~何が危険なのか?~
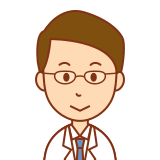
お腹の赤ちゃんが貧血になってしまう事があるんです。重症では胎児水腫(赤ちゃんがむくむ)、最重症では心不全から胎児死亡 となる場合があります。
また、妊娠初期では、流産の確率が上がってしまいます。
3)なのに、家庭内や職場で広まりやすい!!
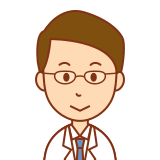
重要なので何度でも繰り返します!
感染力があるのはウイルス血症の時期=症状出現前5日間ほどであり、症状出現時(=診断がつく時期)には、既に他者への感染力はありません。
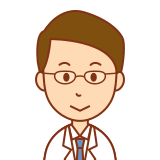
そのため、家庭、学校や保育所、職場などで非常に広まりやすいという特徴があります。
・同居家族が発症した場合、未感染妊婦の50%が感染する。
・医療従事者、学校や保育所勤務者、保健事業従事者の場合、未感染妊婦の20~50%が感染する。
・学校では、感染者と同じクラスの生徒の10~60%が感染する。
という報告があるほどです。
妊婦さん本人はもちろん、同居家族の予防も非常に重要なことがわかるデータですね。
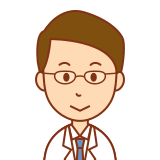
そのため、流行時期には、「全ての人にリンゴ病の可能性がある」という考えでの感染予防が理想的です。
・特に、感冒様症状のある子供との接触には注意しましょう。リンゴ病のウイルス血症の時期である可能性があるためです。
・成人の場合は、感冒様症状にある人はもちろん、感染者の約半数は無症状ですので、無症状であっても接触には注意しましょう。
4)感染が疑われる妊婦の対応は?
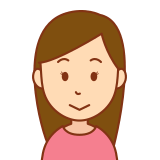
現在妊娠15週ですが、上の子の保育園でリンゴ病が流行っていて、上の子も風邪っぽい症状があります。不安で仕方がありません。
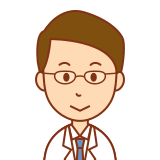
過剰に心配せず、でも、慎重におなかの赤ちゃんの経過を見ていきましょう。
妊娠管理のポイントは、以下になると思います。
1)そもそも、妊婦の5割は抗体を既に持っているため、感染の心配が無い。
→流行期は、妊娠前や妊娠判明時に抗体検査(IgG)を行うのがbetter。陽性なら感染を心配しなくても良いため。
2)感染したかどうかを確かめるには抗体検査(IgGとIgM)を行う。感染から抗体ができるまでのタイムラグを考慮し、感染を疑う行為から2週間はあけて行う(IgM抗体は感染後約10日で、IgG抗体はそれから数日で、陽性になる)。
3)妊娠中に感染してしまった場合:胎児に貧血の兆候が無いか、超音波検査で慎重に経過を見ていく。感染から胎児貧血発症までは8週以内、多くは2~6週であるため、この間は特に慎重に経過を見る(8週間以上問題が無い場合は、それ以降も問題が無いケースがほとんど)。
・母体感染=胎児感染 ではないし、胎児感染=症状出現 でもない。胎児に症状が出現するのは、感染妊婦の4~5%のみ!
・もし胎児貧血になっても、自然に軽快する場合も多くある 。胎児水腫があっても、3割は自然に軽快する、という報告もある。
・妊娠28週以降での感染は、胎児水腫や胎児死亡の発生率が低い。
・重症の場合:胎児に対する有効な治療法は、残念ながらまだない。
5)感染予防
患者の唾液、痰、鼻水を介して感染する飛沫感染・接触感染ですので、一般的な感染予防(手洗い、うがい、マスク)をしっかり行う事が重要です。
また、上のお子さんがいる家庭では、知らないうちに上の子が既に感染している可能性があるため、流行時期には以下の3点を心掛けましょう。
・子供にキスをしない
・子供と食事や飲み物、食器を共有しない
・子供の鼻や口を拭いた後は、手洗いか手指消毒をする
これらは、(日本では最も高頻度に起こる胎児感染症である)先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染の予防にもなります。

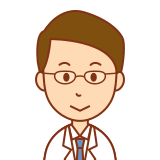
ただし、上のお子さんがいてこれらを完璧に行う事は、正直不可能です。無理のない範囲、過剰にストレスにならない範囲で、ご家族とともに感染予防を頑張ってみてください。
上のお子さんとの関わりも大切になさってくださいね。
6)まとめ
リンゴ病は一般的に軽い病気ですが、妊婦にとっては胎児水腫のリスクが伴うため、感染した(または感染が疑わしい)場合は迅速な対応が求められます。
また、確立した治療法もないため、感染予防(感染者との接触を避け、手洗いや消毒を徹底すること)が重要となります。お腹の赤ちゃんを守るために、正しい知識を身につけた上で、日頃からの注意と適切な管理を心がけましょう。
産婦人科医 まさ
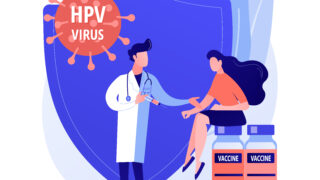
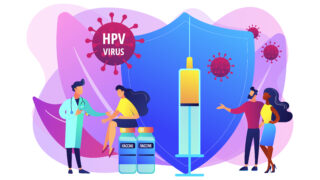






コメント